
小学生のお小遣いはいつから?物語で分かるお金の教え方
2025年9月6日プロローグ:小学生のお小遣い、どうしよう?——全ての親が通る道

「ねぇ、あなた。小学生のお小遣い、どうすればいいのかしら?」
ある日曜の午後。
リビングのソファで雑誌をめくっていた由紀恵が、ふとため息をつきました。
夫の拓也が顔を上げると、彼女は「子どものマネー教育特集」のページを指さしていました。
「ひかりはスーパーに行くたびに『買って!』の大合唱だし、けんたはもうすぐ小学生。お小遣いって、いつから、どのくらい渡せばいいのかしら。あおいも最近、友達とお金の話をすることが増えてきたみたいだし…」
山田家は、どこにでもあるごく普通の家庭です。
そして、子どもの成長とともに避けて通れないのが、「お金」とどう向き合うかという課題。
この記事では、そんな山田家が3人の子どもたちとともに悩み、学び、そして少しずつ成長していく姿を「お金の教育」の物語としてご紹介します。
きっと、物語を通して、ご家庭でも実践できるヒントをきっと見つけていただけるはずです。
[PR]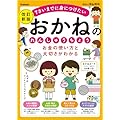
お金の使い方と大切さがわかる おかねのれんしゅうちょう 改訂新版 (学研の頭脳開発)
新品価格
¥1,100から
(2025/9/6 04:28時点)

第1章(準備編):小学生になる前のお小遣い
小学生になる前に与えるお小遣いは、「金額」よりも「体験」に意味があります。
幼児期の子どもにとって、お金はまだ抽象的なもの。
そのため、数字や価値を理解するのは難しい時期です。
しかし、この時期に大切なのは、「すぐに欲しい!」という気持ちを我慢する“待つ力”と、限られた中から何を選ぶかを考える“選ぶ力”を身につけることです。
そして、これらの力は、後のお小遣い管理や金銭感覚の大切な土台となります。
本章では、小学校入学前にどのようにお金と関わらせるべきかについて見ていきます。
物語:魔のチョコレート売り場

その日は、由紀恵さんにとってごく普通のスーパーでの買い物でした。
ですが、カートに乗る3歳のひかりちゃんにとっては、特別な意味を持つ場所がありました。
そう——お菓子売り場です。
そして、お菓子売り場が近づいた途端、ひかりちゃんの目がキラリと輝きました。
「ママ、チョコ! チョコ買う!」
その声に、由紀恵さんは穏やかに答えました。
「ひかり、今日のおやつはもうお家にあるでしょ?」
しかし、一度火がついた「欲しい!」という気持ちは簡単には収まりません。
そして、ひかりちゃんはカートから身を乗り出し、泣き叫び始めました。
「ギャー! チョコ! チョコぉぉぉ!」
この鳴き声によって、周囲の買い物客の視線が由紀恵さんに突き刺さります。
そして、由紀恵さんは焦りと恥ずかしさで胸がいっぱいになりました。
このまま、また泣き声に負けて欲しがるままに買い与えてしまうとも考えました。
しかし、由紀恵さんはふと思い直しました。
「ひかり、よく見て。チョコレートと、あっちのクッキー。ひかりが“本当に”食べたいのはどっち? ひとつだけ、ひかりが選んでいいよ」
由紀恵は叱るのではなく、「選ばせる」という機会を与えたのです。
この突然の提案に、ひかりちゃんはピタリと泣き止み、真剣な表情でお菓子を見つめました。
そして小さな指でクッキーを指さします。
「こっち!」
由紀恵さんはにっこり微笑んで言いました。
「すごいね! 自分で選べたね!」
そして笑顔のままレジへと向かいました。
これは、ひかりちゃんにとって、ひとつの小さな選択でした
しかし、由紀恵さんは確かな手応えを感じていたのです。
【解説】幼児期に育てたいのは「待つ力」と「選ぶ力」
心理学の視点では、3歳頃は自我が芽生え、欲求をコントロールし始める大切な時期です。
スーパーで「買って!」とねだる行為は、親にとっては困りごとに感じられます。
しかし、それは子どもの「自分の意志」が育ってきた証でもあります。
特に、この時期に特に育みたいのが、「待つ力」です。
これは、将来の目標のために現在の欲求を我慢する力、つまり「自制心」の土台となります。
そのため、いきなり「ダメ!」と突き放すのではなく、「お家に帰ってからね」と先の見通しを伝えたり、「お買い物が終わったら公園で遊ぼうね」と別の楽しみを提示したりすることが効果的です。
また、お金の役割を伝えるには、おもちゃのお金を使った「お買い物ごっこ」が最適です。
これは、子どもがお金と物の「交換の概念」を学ぶ良い機会になります。
まずは、「このお金を払って、お菓子をひとつだけもらえるんだよ」と教えましょう。
さらに「ありがとう」と感謝の言葉を添えることで、お金が単なる紙切れではなく、人とのやり取りの中で使われる大切なツールであることを伝えられます。
この時期のゴールは、お金の価値を完全に理解することではありません。
「世の中にはルールがあること」や「自分の欲求を少しだけコントロールできること」を体感できれば、第一章はクリアといえます。
【やりがちな失敗】「泣き声」に負けて、言いなりになってしまう
お店で子どもが大声で泣き叫ぶと、親は慌ててしまうもの。
そのため、周囲の視線が気になって「今回だけよ」とつい言いなりになってしまう親御さんは少なくありません。
しかし、これを繰り返すと、子どもは「泣けば欲しいものが手に入る」と学習してしまいます。
ここで大切なのは、親が一貫した態度を示すこと。
時には、「ダメなものはダメ」と伝える勇気も時には必要です。
そして、その場を一旦離れて、子どもが落ち着いてから「なぜ今日は買ってあげられないのか」を簡潔に優しく説明してあげましょう。
親が衝動的な感情に流されず、冷静に対応することで、子どもは「泣いてもどうにもならない」と学びます。
そして、少しずつ自分の感情をコントロールできるようになっていくのです。
これは将来、お金を管理する際に衝動買いを避けるための大切な力にもつながります。
第2章(低学年編):「小学生のお小遣い」ルールと金額

いよいよ、お小遣いデビューです。
小学生になると、子どもたちの世界は一気に広がります。
そして、友達とのお金のやり取りや、おもちゃ屋さんでのお買い物など、お金に触れる機会もぐっと増えていきます。
この章では、けんたくんが小学生になり、初めて小学生のお小遣いを手にした山田家の物語を通して、低学年のうちに身につけておきたい「お金の見える化」と、そのために役立つ具体的なルールについて解説していきます。
物語:500円玉の冒険
小学校に入学して3ヶ月。
けんたくんは、初めてのお小遣いとしてピカピカの500円玉を由紀恵さんから手渡されました。
「やったー! これでコロコロコミックが買えるぞ!」
けんたくんは目を輝かせ、早速、友達と本屋へ向かいました。
そして、目当ての漫画を手にレジへ行き、500円玉を差し出しました。
しかし、店員さんは首を横に振ったのです。
「ごめんね、お兄ちゃん。消費税がかかるから、ちょっとだけ足りないんだよ。」
けんたくんはがっくりと肩を落としました。
まさか、値段のほかに「税金」というものがあるなんて、思いもよらなかったのです。
コロコロコミックを諦め、しょんぼりと家に帰ったけんたくんに、パパの拓也さんが声をかけました。
「どうした? 元気ないな。」
事情を聞いた拓也さんは、けんたくんに一冊のノートと鉛筆を手渡しました。
「けんた、これが『お小遣い帳』だ。君がもらった500円が、どこへ冒険に出かけるのか記録してみよう。使った分をここから引いていくんだ。」
拓也さんは、お金の動きを「見える化」する楽しさを教えました。
そして、けんたくんは、500円玉がまるで旅をするように、自分の手元から何に使われたのかを記録していくことに、少しワクワクし始めました。
この日から、けんたくんにとって500円玉は、ただの硬貨ではなく、大切な「パートナー」になったのです。
【解説】「数の概念」が育つ小学生には「見える化」が効く!
7歳頃は、子どもが具体的なモノを通して論理的に物事を考えられるようになる時期です。
そしてこの時期、小学生のお小遣いは、算数の力を実践的に伸ばす絶好のチャンスです。
お金の流れを「見える化」することで、より効果的な学びにつながります。
👉お小遣い帳はシンプルに
最初から完璧を目指す必要はありません。
まずは「もらった日」「つかったもの」「のこり」の3項目だけで十分です。
大切なのは、記録を通してお金がどのように増えたり減ったりするのか、その流れを客観的に把握する習慣を身につけることです。
最近では、子ども向けの楽しいお小遣い帳アプリもたくさんありますので、取り入れてみるのもよいでしょう。
👉貯金のモチベーション維持のコツ
「貯金しなさい」と口で言うだけでは、なかなか続きません。
大切なのは、目標を達成する喜びを体験させてあげることです。
たとえば、「〇〇を買うために、あと〇円!」と書いた紙を貼った透明の貯金箱を用意するのがおすすめです。
お金が少しずつ貯まっていく様子が目に見えることで、子どもは達成感を感じやすくなります。
この時期のゴールは、予算内でやりくりする感覚を養い、「計画することの大切さ」と「目標を達成する喜び」を知ることです。
たとえ失敗しても、その経験を親子で一緒に振り返り、次に活かしていく姿勢が大切です。
【やりがちな失敗】使い方に口を出しすぎてしまう
子どもが親から見て「くだらないもの」を買ったときは要注意。
この場合、「そんな無駄なもの買って!」と感情的に叱ってしまうのは避けましょう。
このような言葉は、子どもの「欲しい」という気持ちや価値観を否定してしまいます。
その結果、お金を使うことに萎縮してしまったり、親への不信感につながったりする可能性があります。
たとえ親からは失敗に思える買い物でも、それは子どもにとって大切な学びの機会です。
重要なのは、親が「失敗を責めない」ことです。
そして「次はどうしたい?」と問いかけ、子ども自身に考えさせることが成長につながります。
この時期に、「自分の意思でお金を使えた」という成功体験を積むことが、将来の自立した金銭感覚の土台になります。
だからこそ、お金の使い方を親が見守りながら、導く姿勢を大切にしましょう。
第3章(高学年編):小学生のお小遣い、「働く」をどう教える?
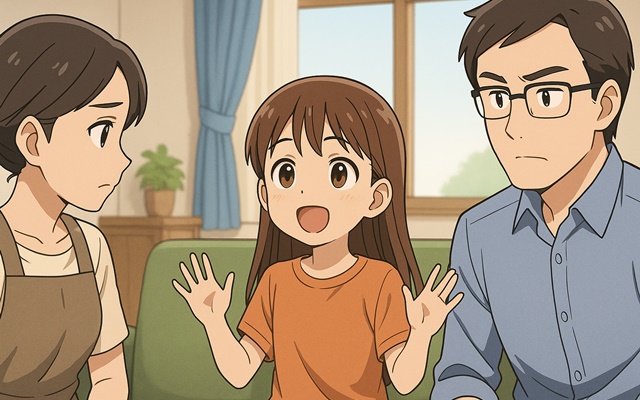
小学高学年になると、子どもたちは社会の仕組みに関心を持ち始めます。
そして、小学生のお小遣いも単なる「もらうお金」から、「自分の力で得るお金」へと意味合いが変わっていく時期です。
この章では、中学受験を意識し始めたあおいさんが、お小遣いの増額をめぐって両親と交渉する物語を通して、子どもに「働くことの尊さ」や「お金がどのように生み出されるのか」を伝える方法について解説していきます。
物語:お駄賃アップのプレゼンテーション
小学5年生になったあおいちゃんは、リビングに家族を呼び集めました。
そして、いつもより少し緊張した面持ちで手作りの資料を広げ、こう宣言しました。
「私、お小遣いを月500円から700円にアップしてほしいです!」
拓也さんと由紀恵さんは顔を見合わせ、驚きを隠せませんでした。
しかし、あおいちゃんは動じることなく、プレゼンテーションを続けました。
「理由は、今の500円では将来のために欲しい参考書が買えないからです。その代わり、これまでのお風呂掃除に加えて、毎週土曜日の朝は玄関の掃除とゴミ出しを担当します。これは、家族が気持ちよく週末を過ごすための『労働価値』に見合うと考えています。」
これは単なるおねだりではありませんでした。
自分の要求と、その対価として提供できる価値を真剣に考えた、あおいちゃんの「働くこと」への第一歩だったのです。
拓也さんと由紀恵さんは、そのしっかりとした交渉に感心しました。
「すごいね、あおい。ママとパパも、その提案に大賛成だよ。」
あおいちゃんは誇らしげな笑顔を見せました。
そして、この小さな交渉が、彼女のお金に対する考え方を大きく変えるきっかけとなったのです。
【解説】論理的思考が育つ高学年には「社会とのつながり」を!
10歳頃になると、子どもは物事を多角的にとらえ、抽象的な概念も理解できるようになります。
だからこそ、小学生のお小遣いを通して「お金がどこから来て、どこへ行くのか」といった、より大きな社会の仕組みに興味を持つ絶好のタイミングです。
👉お金は社会の血液
お金がただの道具ではないことを伝えてあげましょう。
「パン屋さんは、美味しいパンを売ってお金をもらう。そのお金で小麦粉を買ったり、お店の電気代を払ったりするんだよ」
このように、身近なお店を例に出すと分かりやすいでしょう。
そうすることで、お金が社会をぐるぐると巡っていることをイメージできるようになります。
👉「働く」の価値は一つじゃない
「働くこと」の価値は、必ずしもお金を稼ぐことだけではありません。
そこで、お医者さんやケーキ屋さんのような職業だけでなく、NPOの活動や地域のボランティアなど、直接的なお金儲けとは異なる「社会貢献」という価値があることも伝えてみましょう。
これにより子どもの視野が広がり、将来の夢を考えるきっかけになります。
👉この時期のゴール
お手伝いなどを通して、「労働の対価としてお金を得ること」の意味を理解し、そのお金を通じて「社会と自分はつながっている」と感じられることが目標です。
これが、お金を大切にする心や、将来のキャリアを考える上での大切な土台となります。
【やりがちな失敗】すべての「お手伝い」を報酬制にしてしまう
良かれと思って「靴並べ10円」「お皿洗い30円」など、すべての家事を細かく報酬制にしてしまうと、「お金をもらえないならやらない」という思考に陥りがちです。
これは、子どもが「家族の一員としての役割」を学ぶ機会を奪ってしまう可能性があります。
お小遣いとお手伝いのルールには、メリハリをつけることが大切です。
たとえば、「自分の部屋の片付け」や「食後の食器を運ぶ」といった、家族の一員として当たり前に担うべき役割は無報酬にしましょう。
その一方で、「車の洗車」や「庭の草むしり」など、特別な労働や普段の生活にプラスして行ってもらうお手伝いに対しては報酬を支払うのがおすすめです。
こうすることで、「働くこと」と「家族としての助け合い」を区別して教えられます。
エピローグ:小学生のお小遣い、本当に大切なたった一つのこと

山田家のマネー育英物語、いかがでしたでしょうか。
物語の主人公たちも、少しずつ成長しています。
3歳のひかりちゃんは今でもお店で「買って!」と言うことがありますが、2つのうち1つを真剣に選べるようになりました。
小学校低学年のけんたくんは、お小遣い帳をつけながら、次に欲しいゲームソフトを買うための計画を立てています。
そして高学年のあおいさんは、自分でお金を管理する責任と楽しさを感じながら、最近ではニュースの経済情報にも関心を持つようになりました。
特別な教材や難しい理論は必要ありません。
本当に大切なのは、子どもの成長に合わせて、日々の生活の中で「これは何円だね」「パパは働いてお給料をもらっているんだよ」といったように、お金についてオープンに話すことです。
子どものお金に対する価値観は、親の背中を見て育ちます。
最高の金融教育は、愛情あふれる家庭での「対話」の中にあるのです。
さあ、あなたも今日から、お子さんと小学生のお小遣いについて、話を始めてみませんか。
[PR]
新品価格
¥1,872から
(2025/9/6 04:44時点)

投稿者プロフィール

-
「人の心理をもっとロジカルに分析できないか」という考えのもと、人間心理の研究と診断開発に一貫して携わってきた専門家。
心理学者・多湖輝氏が主催された「多湖輝研究所」に所属した経験を活かし、診断テスト開発者として30年以上にわたり、多くの企業向けに様々な診断コンテンツを開発。
特に以下の分野で実績を保有しています。
・男女の心理分析: 大手結婚情報誌向け「結婚相性診断テスト」
・性格・学習分析: 大手メーカー向け「教育診断テスト」
最新の投稿
 夫婦のヒント2025年12月2日夫が約束を守らない原因は脳?脳科学で導く解決策【診断付】
夫婦のヒント2025年12月2日夫が約束を守らない原因は脳?脳科学で導く解決策【診断付】 恋愛のヒント2025年11月28日恋愛会話を心理学で攻略!脳科学が教える【魔法のフレーズ実例】
恋愛のヒント2025年11月28日恋愛会話を心理学で攻略!脳科学が教える【魔法のフレーズ実例】 お金のヒント2025年11月25日夫婦の金銭感覚違いで離婚? 心理学で解く合わない原因と解決策
お金のヒント2025年11月25日夫婦の金銭感覚違いで離婚? 心理学で解く合わない原因と解決策 夫婦のヒント2025年11月18日「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準
夫婦のヒント2025年11月18日「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準