なぜ投資で失敗するのか?

自分が投資で失敗する理由、理解できていますか?
雑誌で「おすすめ銘柄」と紹介されていた株を買ったのに、なぜか値下がりしてしまった…。
人気のYouTuberのアドバイス通りに動いたのに、タイミングが合わずに結局損切りに…。
あなたには、こんな経験はありませんか?
多くの人が「投資で成功するには、“どの銘柄が上がるか”という情報や、“チャートの読み方”といったテクニックが重要だ」と考えています。
確かに、それらも大切な要素です。
しかし、それだけでは長期的に資産を築くことは難しいのです。
実は、投資の成否を分ける、もう一つの非常に重要な要素こそが、「メンタル」です。
たとえ優れた情報やテクニックを持っていても、いざ自分のお金が動く局面になると、私たちは驚くほど非合理的な判断をしてしまうことがあります。
その理由は、人間の脳に根深く刻まれた「心のクセ」によるものです。
この記事では、多くの投資家が知らず知らずのうちに陥ってしまう心理的な落とし穴を、代表的な5つのタイプに分けて解説していきます。
[PR]


投資で失敗する5つの心理的落とし穴
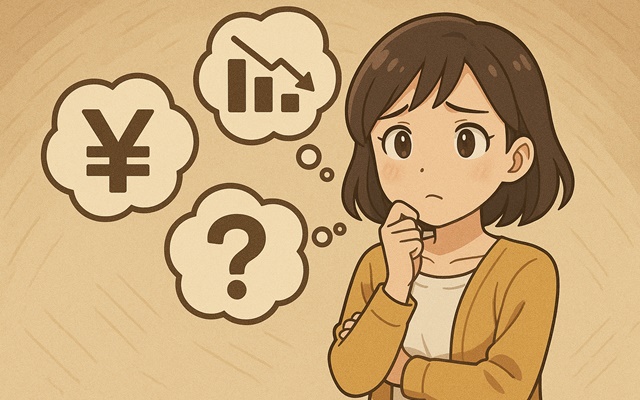
投資で失敗してしまう人には、ある共通の特徴があります。
それは、感情に左右された判断をしてしまうこと。
たとえ、どれだけ豊富な情報や高いスキルを持っていても、いざ自分のお金が動く場面になると、冷静さを保つのは簡単ではありません。
そのくらい、人間心理とは、投資に大きな影響を及ぼします。
本章では、多くの投資家がついやってしまいがちな5つの「心の落とし穴」を、具体的なタイプ別に分けてご紹介します。
①コツコツドカン型(プロスペクト理論)
あなたは、小さな利益をコツコツ積み重ねるのが得意なタイプではありませんか?
たとえ、数千円〜数万円の利益でも着実に確定させる。
そして、「今日もいい感じ!」と手堅く達成感を味わう。
しかし、一度損失が出始めると、なかなか株を手放せない…。
そのため、そのままズルズルと持ち続け、最終的に大きな損切りを迫られたり、含み損を抱えたまま“塩漬け”状態になってしまったり…。
そして、これまでコツコツと積み上げてきた利益が、たった一度の大きな損失、いわゆる「ドカン」で一気に吹き飛んでしまう。
そんな経験、思い当たる方も多いのではないでしょうか。
これこそが、「コツコツドカン型」の典型的なパターンです。
この行動の裏には、プロスペクト理論という心理学的な背景があります。
人間は、「得をすること」よりも「損をしないこと」に対して、より強い感情的な反応を示す傾向があります。
つまり、
✔ 小さな利益を早めに確定してしまうのは、「せっかくの利益が減るのはイヤだ」という心理。
✔ 損切りができずに塩漬けにしてしまうのは、「損を確定するのが怖い」という心理。
このような心理が繰り返されることで、少しずつ利益を積み上げても、たった一度の“ドカン”で全てを失ってしまうという悪循環に陥ってしまうのです。
②イナゴタワー型(ハーディング効果)
SNSやニュースで、「この株、爆上げ中!」と話題になると、つい気になってしまう。
みなさんは、そういった経験がありませんか?
どうしても「今買わなきゃ乗り遅れる!」と、深く考えずにその銘柄に飛びついてしまう。
けれど、いざ買ってみると、買ったところが株価の“天井”で、そこから価格は急落…。
そして、気づけば、大きな含み損を抱えている。
まさに、これは「イナゴタワー型」と呼ばれる典型的なパターンです。
イナゴタワーとは、群がるイナゴのように、情報に飛びついた投資家たちによって急騰した株価が、熱が冷めるとともに一気に落ちていく現象を表しています。
この行動の背景には、ハーディング効果(同調効果)と呼ばれる心理があります。
これは、多くの人が取っている行動を目の当たりにすると、「自分も同じようにしなければ」と無意識に思い込み、冷静さを欠いた判断をしてしまうという心理現象です。
特にSNSや匿名掲示板などでは、根拠の乏しい情報や煽り文句が飛び交い、「早く乗らないと損する!」という焦りが生まれがちです。
その結果、冷静な分析を置き去りにしたまま、ババをつかんでしまうというケースが後を絶ちません。
群衆の熱気に飲み込まれそうになったときこそ、一歩立ち止まることが大切です。
その情報は本当に信頼できるのか?
自分の投資スタイルや戦略に合っているのか?
そう自問しながら判断する冷静さと自律心こそが、長期的な投資成功には欠かせないのです。
③自分は大丈夫型(正常性バイアス・自信過剰)
あなたは過去に、たまたまうまくいった投資経験がありませんか?
たとえば、少額で買った株が偶然にも急騰して利益を得られた。
あるいは、市場全体が下落している中で、自分だけがうまく回避できた。
そんな“たまたま”の成功体験がきっかけで、人は気づかぬうちに過信してしまうものです。
これが、「自分は大丈夫型」の典型的なパターンです。
このタイプは、データや分析といった根拠ではなく、感覚的な自信に支えられて行動する傾向があります。
そして、その背景にあるのが、正常性バイアスと自信過剰という2つの心理です。
正常性バイアスとは、たとえ目の前で異常事態が起きていても、「きっと大丈夫だろう」「自分には関係ない」と都合よく解釈して、危険性を過小評価してしまう心理傾向です。
そのため、市場の明らかなリスクも楽観的にとらえてしまい、判断を誤ることがあります。
さらに、自信過剰は、自分の判断力や成功の可能性を過大評価してしまう心理です。
この影響で、リスク管理が甘くなると、
- 特定の銘柄に資金を集中させてしまう
- 分散投資を怠る
- 根拠のない判断でポジションをとる
といった行動につながりやすくなります。
結果として、市場の急変や予想外の事態が起きたときに、想像を超える損失を被ってしまうリスクが高まるのです。
自分を過信せず、常に謙虚な姿勢でリスクと向き合うこと。
それこそが、この落とし穴から抜け出すために最も大切な心構えです。
④機会損失おばけ型(FOMO:Fear of Missing Out)
周囲の投資家が大きな利益を出している話を聞いたり、特定の銘柄が急騰しているニュースを目にしたとき、「このチャンスを逃したら、もう二度と巡ってこないかもしれない…」という強い焦りや不安に駆られたことはありませんか?
そのため、「もし、あのとき買っていれば…」という過去の後悔が頭から離れない。
そして、次の投資では冷静さを欠き、ただの直感だけを頼りに無謀な取引に走ってしまう。
これがまさに、「機会損失おばけ型」の投資で失敗するパターンです。
実は、この行動の背景には、近年注目されている心理現象があります。
それが、「FOMO(Fear of Missing Out=取り残されることへの恐れ)」です。
人はFOMOに囚われてしまうと、本来の投資戦略や自分のリスク許容度を見失います。
そして、目先の利益ばかりに目が向いてしまうのです。
まるで、目の前に現れた“機会損失おばけ”に取り憑かれたかのように、ろくに分析もせずに話題の銘柄に飛びついてしまう。
そして、結果的に高値掴みや損失を招くことになりかねません。
この落とし穴から抜け出すには、他人の成功と自分を比べないこと。
そして、「自分の投資目的」「自分のリスク許容度」といった軸を、しっかりと見つめ直すことが何より重要です。
情報に振り回されず、自分自身の投資スタンスを守ることこそが、ブレない投資への第一歩です。
⑤情報過多パニック型(分析麻痺)
投資に関する本を何冊も読み、YouTubeで経済ニュースをチェックし、SNSで著名な投資家の意見を参考にする。
もしかして、あなたはそんな熱心に情報を集めるタイプではありませんか?
しかし、その結果、情報が山のように積み上がり、頭の中が情報でいっぱいになる。
そして、結局なにも決断できないまま時間だけが過ぎてしまう。
これが、まさに「情報過多パニック型」の特徴です。
このタイプが陥りやすいのが、分析麻痺(Analysis Paralysis)という状態です。
人は完璧な判断をしようとすればするほど、「もっと情報が必要だ」と感じてしまう。
そして、大切な判断が先延ばしになってしまう。
その結果、せっかくのチャンスを目の前で逃してしまうのです。
この落とし穴を避けるために必要なのは、「情報の量」ではなく「質」を見極める力。
そしてもうひとつ大切なのは、ある程度の情報が揃った段階で、「完璧じゃなくても行動する勇気」を持つことです。
投資において、慎重さはもちろん大切です。
しかし、慎重すぎて一歩も踏み出せなければ、何も始まりません。
大切なのは、自分の投資目的とリスク許容度に合った「納得できる判断」を、自分のタイミングで下すことなのです。
タイプ別 投資で失敗しないための処方箋

ここまで、投資家が陥りやすい5つの心理的な落とし穴について見てきました。
読み進める中で、「これ、自分のことかも…」と感じた方も、少なくないのではないでしょうか。
実はその“気づき”こそが、投資で失敗を減らすための第一歩です。
しかし、それだけでは不十分。
本当に大切なのは、そのクセを自覚したうえで、どう向き合い、どう対処していくかということ。
「分かってはいるけど、やめられない…」。
そんな状態から抜け出すためには、具体的な行動指針が必要です。
そこで次章では、5つのタイプそれぞれに合わせた、実践的な“処方箋”をご提案します。
①コツコツドカン型|ルールを“感情が入る前”に決めよう
心の声:
「含み損だけど、売らなければ負けじゃない」「もう少し待てば、買った値段まで戻るはず…」
あるある投資での失敗談:
投資を始めたAさん。
複数の銘柄に投資し、+5%の利益が出たら売るというルールで利益を積み重ねていました。ある日、主力銘柄の一つが-10%下落。
「これは優良株だから大丈夫」と損切りせず保有を続けた結果、株価はさらに下落。
気づけば、今までの利益をすべて吹き飛ばすほどの含み損になってしまいました。
処方箋(対策):
- 「買う前」に出口を決める:
感情が入りやすい売買時ではなく、投資する銘柄を選ぶ段階で、「買値から-8%で損切り」「+20%で利益確定」のように、具体的な売却ルールを明確に決めておきましょう。
これにより、損失をズルズルと拡大させてしまうことを防ぎます。 - 逆指値注文を活用する:
決めた損切りラインには、あらかじめ逆指値(ストップロス)注文を入れておくことを強く推奨します。
これにより、自動で売却されるため、感情が介入せずに機械的に損失を限定できます。 - 損益を「率(%)」で考える:
損失が出た際に、「10万円の損失」と金額で考えると精神的な負荷が増します。
これを「投資資金全体の2%の損失」といったように、ポートフォリオ全体に対する「率(%)」で捉えることで、冷静な判断がしやすくなります。
個別の損益に一喜一憂せず、全体最適を意識しましょう。
②イナゴタワー型|「みんなが買ってる」では勝てない
心の声:
「みんなが買ってるから大丈夫だろう」「この波に乗り遅れたくない!」
あるある投資での失敗談:
SNSで「〇〇コインが爆上がり中!」という投稿が飛び交っているのを見たBさん。
詳しくは分からないまま、「今すぐ買わないと」と焦り、急いで飛びつきました。
しかし、Bさんが買った直後が価格のピーク。
その後、価格は暴落し、典型的な「高値掴み」となってしまいました。
処方箋(対策):
- SNSは「きっかけ」に、判断は「自分」で:
SNSやニュースで話題になっている銘柄を、それらの情報だけで投資判断を下すのは非常に危険です。
必ず、企業の公式サイト、IR情報、決算報告書といった一次情報にあたり、自分自身で分析する習慣をつけましょう。 - 他人の「答え」ではなく自分の「言葉」で説明できるか問う:
なぜその銘柄に投資するのか、自分の言葉で明確に説明できますか?
自分自身で具体的な理由を述べられるものだけに、投資するようにしましょう。 - 投資前にチェックリストを作る:
感情的な判断を防ぐために、自分なりの投資前チェックリストを作成しましょう。
例えば、「事業内容は明確に理解できるか?」「競合優位性はあるか?」「将来性や成長性は期待できるか?」など、客観的な視点で評価できる項目を設定し、全てクリアできた場合のみ投資するというルールを設けるのが効果的です。
③自分は大丈夫型|「自信」と「過信」は紙一重
心の声:
「これまで上手くいったから、次も大丈夫」「暴落なんてそうそう起きない」
あるある投資での失敗談:
ビギナーズラックで利益を出したCさん。
すっかり自信をつけ、「自分には投資の才能がある」と思い込みました。
そして、信じ込んだ一つの成長株に資金を集中させました。
しかし、その企業の不祥事が発覚し、株価は連日のストップ安。
Cさんは資産の大部分を失ってしまいました。
処方箋(対策):
- 分散を徹底する:
投資の世界の金言である「卵は一つのカゴに盛るな」を肝に銘じましょう。
特定の銘柄や業種、国に資金を集中させるのではなく、銘柄、業種、地域、そして時間(積立投資など)を分散することで、一つの要因で資産全体が大きなダメージを受けるリスクを軽減できます。 - 投資ノートをつける:
自分の投資行動を振り返るために、投資ノートをつけることを強くお勧めします。
なぜその銘柄を売買したのか、その時の感情など、詳細に記録しましょう。
後から見返すことで、自分の成功パターンだけでなく、失敗パターンや過信に陥っていた瞬間を把握し、冷静さを取り戻すきっかけになります。 - 常に最悪の事態を想定する:
投資をする前に、「この銘柄の価値がもし半分になったら、自分の生活はどうなるか?」と常に自問自答してください。
さらに、「投資資金が全てなくなったらどうなるか?」と想像力を働かせ、自分が許容できるリスクの範囲内で投資を行うようにしましょう。
④機会損失おばけ型|「逃した魚」は忘れてOK
心の声:
「あの時買っておけば今頃…」「次のビッグウェーブだけは絶対に逃せない!」
あるある投資での失敗談:
株価が右肩上がりの銘柄を見て、「買いたいけど、もう上がりすぎかな…」と躊躇しているうちに、さらに高騰。
「ああ、あの時買っておけば…」と強く後悔したDさん。
次に別の急騰銘柄を見つけた時、「今度こそ乗り遅れるな!」と、高値にもかかわらず焦って飛びつき、結局、調整局面の下げに巻き込まれてしまいました。
処方箋(対策):
- 「休むも相場」を心に刻む:
投資チャンスには、「今を逃したら終わり」ということは決してありません。
焦って自分のルールや分析に合わない投資をするくらいなら、何もしないで待つ方が、はるかに賢明な判断です。
冷静な判断ができない時は、一歩引いて市場を眺める「休む勇気」が重要です。 - 投資計画を立て、それ以外はやらない:
自分の投資スタイルや目標を明確にした投資計画を立てましょう。
例えば、「私は長期の積立投資がメインだ」「高配当株投資に集中する」といった具体的な方針です。
一度計画を立てたら、魅力的な「もうけ話」が出てきても、計画外の投資は見送る強い意志を持つことが大切です。 - 完璧なタイミングは狙わない:
市場の底値で買い、天井で売るという完璧なタイミングを狙うことは、プロの投資家でも不可能です。
そのように「完璧」を追い求めることは、かえって機会損失の不安を増幅させ、焦りにつながります。
自分のルールや分析に基づきエントリーできれば、それが自分にとってのベストなタイミングだと割り切ることが、精神的な安定と冷静な判断につながります。
⑤情報過多パニック型|考えすぎて動けない症候群
心の声:
「まだ情報が足りない気がする」「Aアナリストは買いと言っているが、Bエコノミストは売りと言っていて…」
あるある投資での失敗談:
真面目な性格のEさん。
投資を始めるにあたり、経済ニュースを毎日チェックし、関連書籍を10冊以上読破。
様々なアナリストレポートにも目を通しました。
しかし、情報を集めれば集めるほど、様々な懸念点が見えてきてしまい、結局「怖くて何も買えない」状態になり、その間に狙っていた銘柄はどんどん上がっていってしまいました。
処方箋(対策):
- 情報源を「少数精鋭」に絞る:
人は、情報量が多くなりすぎると、かえって混乱するものです。
インプットする情報源は、信頼できるもの3~5個程度に厳選し、それ以外の不確かな情報は見ないようにシャットアウトしましょう。 - 100点の判断はないと知る:
投資に「絶対」はありませんし、完璧なタイミングや判断も存在しません。
100点の確信を待つのではなく、70点程度の確信が持てたら、まずは少額からでも行動に移してみましょう。
「走りながら考える」くらいの柔軟な気持ちが、分析麻痺を乗り越える上で重要です。 - インデックスファンドから始める:
個別株の詳細な分析が難しいと感じるなら、まずは日経平均やS&P500といった市場全体に連動するインデックスファンドへの積立投資から始めることを強くお勧めします。
これにより、個別の企業分析のストレスから解放され、市場全体の成長の恩恵を効率的に受けられます。
まとめ:投資で失敗しないために!

ここまで、投資で失敗しがちな5つの心理パターンをご紹介してきました。
あなた自身に、思い当たるタイプはあったでしょうか?
ですが、たとえ当てはまっていたとしても、落ち込む必要はまったくありません。
誰もが何かしらの「心のクセ」を抱えながら、投資に向き合っています。
大切なのは、「自分にはこういう弱点があるんだ」と冷静に認識すること。
そして、その弱点を責めるのではなく、うまく付き合っていく仕組みを作ることです。
今日ご紹介した「処方箋」の中から、自分に合いそうなものをひとつ選んで、まず行動に移してみてください。
自分の心のクセを理解し、感情を味方につけていくことこそが、情報やテクニック以上に、あなたを長期的に成功する賢い投資家へと導いてくれる、最強の武器になるはずです。
[PR]
ブシロードクリエイティブ(bushiroad creative) 7歳から学べる投資ゲーム (2-4人用 15-30分 7才以上向け) ボードゲーム
新品価格
¥1,458から
(2025/7/24 08:01時点)

投稿者プロフィール

-
「人の心理をもっとロジカルに分析できないか」という考えのもと、人間心理の研究と診断開発に一貫して携わってきた専門家。
心理学者・多湖輝氏が主催された「多湖輝研究所」に所属した経験を活かし、診断テスト開発者として30年以上にわたり、多くの企業向けに様々な診断コンテンツを開発。
特に以下の分野で実績を保有しています。
・男女の心理分析: 大手結婚情報誌向け「結婚相性診断テスト」
・性格・学習分析: 大手メーカー向け「教育診断テスト」
最新の投稿
 お金のヒント2025年12月19日彼氏にお金貸してと言われたら?関係を壊さない断り方と心理診断
お金のヒント2025年12月19日彼氏にお金貸してと言われたら?関係を壊さない断り方と心理診断 夫婦のヒント2025年12月2日夫が約束を守らない原因は脳?脳科学で導く解決策【診断付】
夫婦のヒント2025年12月2日夫が約束を守らない原因は脳?脳科学で導く解決策【診断付】 恋愛のヒント2025年11月28日恋愛会話を心理学で攻略!脳科学が教える【魔法のフレーズ実例】
恋愛のヒント2025年11月28日恋愛会話を心理学で攻略!脳科学が教える【魔法のフレーズ実例】 お金のヒント2025年11月25日夫婦の金銭感覚違いで離婚? 心理学で解く合わない原因と解決策
お金のヒント2025年11月25日夫婦の金銭感覚違いで離婚? 心理学で解く合わない原因と解決策



コメント